太陽光発電蓄電池の設置時にかかる工事費用の相場と注意点

太陽光発電蓄電池は、災害時の電力供給や省エネに役立ち、効率的な運用が期待されます。設置工事は1~2日で完了し、費用は容量や品質によって異なります。補助金制度や0円ソーラーリース契約を活用することで、コストを抑えた導入が可能です。
目次
蓄電池の仕組みと注目されている背景

蓄電池は太陽光発電と連携し、災害時や日常の省エネに役立つ装置として注目されています。技術進歩により、効率的な運用と長期的なコスト削減が期待されています。
◇蓄電池の仕組み

蓄電池は外部から供給された電気を化学反応によって貯蔵し、必要なときに放電して利用する装置です。
特に太陽光発電システムと連携させることで、昼間に発電した余剰電力を蓄電池に充電し、夜間や日照が少ない時間帯に放電して使用することができます。
主にリチウムイオン型が利用されており、このタイプは軽量でエネルギー密度が高いことが特徴です。そのため、設置スペースが限られている住宅でも効率的に運用することが可能です。
さらに、近年の技術進歩により、充放電サイクル寿命が延び、長期的な運用コストの削減につながると期待されています。
◇蓄電池が注目されている理由

災害時の非常用電源として利用できることは、蓄電池の大きな利点です。 例えば、大規模災害や台風、地震などによる停電に備え、冷蔵庫や照明などの最低限必要な家電を動かすための電力を確保できる点が、安心感を提供しています。
また、電力会社の買い取り価格が年々低下している現状では、太陽光発電で得た電力を自家消費する方が光熱費削減に有効であると分析されています。
最終的には、費用と性能を考慮しながら、日常の省エネと災害対策を兼ね備えた方法として、蓄電池の導入は有効な解決策といえるでしょう。
【あわせて読みたい】
家庭用蓄電池の容量はどれくらい必要?

家庭用蓄電池の導入を検討する際、容量の選び方は電力の使い方や設置目的によって大きく異なります。停電対策や電気代削減など目的に合った容量を選ぶことが重要です。
◇家庭用蓄電池の容量を理解しよう
家庭用蓄電池の容量は「kWh(キロワットアワー)」という単位で表されます。これは「1kWの電力を1時間使う=1kWh」という意味で、日常的な電力消費量の目安になります。例えば、1000Wの電子レンジを1時間連続で使用すると1kWhを消費する計算です。
家庭でよく使う冷蔵庫は200W前後、液晶テレビは50W程度で、使用時間を掛け合わせれば必要な電力量が分かります。加えて、蓄電池を検討する際は「サイクル数」も重要です。サイクル数とは、フル充電からフル放電までを1回とする充放電の回数のことで、リチウムイオン電池では6,000〜12,000サイクルが一般的な寿命とされています。
1日1回の充放電であれば10年以上の使用が見込め、導入コストと寿命を比較するうえで大切な指標となります。
◇ライフスタイルから逆算する容量の目安

必要な蓄電池容量は、世帯人数や生活習慣によって変わります。単身世帯では5kWh前後でも最低限の電力をまかなえますが、4人以上の世帯や共働き家庭では10kWh以上が安心です。
例えば冷蔵庫(200W×24時間=約4.8kWh)、エアコン(750W×5時間=約3.75kWh)、電子レンジ(1400W×0.5時間=約0.7kWh)、テレビや照明などを加えると、合計で1日10〜15kWhに達する家庭も珍しくありません。停電時にこれをすべて蓄電池でカバーするのは現実的ではないため、優先順位をつけて必要量を逆算することが大切です。
例えば「冷蔵庫・照明・スマホ充電」など生活の最低限を確保するなら5〜7kWh程度でも十分です。一方「エアコンやIHクッキングヒーターも使用したい」となると、15kWhクラスの大容量が求められます。導入前に家庭で優先する家電を洗い出すことが、最適な容量選びにつながります。
◇停電時に備える容量と電圧選び

災害対策として導入する場合は、容量に加えて電圧対応も考慮すべきです。家庭用蓄電池には100V対応と200V対応のタイプがあります。
100V対応であれば冷蔵庫・照明・通信機器の充電など、最低限の家電は問題なく使えます。一方、エアコンやIHなどの大型家電を使用するには200V対応が必要です。ただし200V家電は消費電力が大きく、蓄電池残量の減りが早いため、容量に余裕を持たせなければなりません。
また、停電時に「全負荷型」で家全体へ電力を供給するのか、「特定負荷型」で一部の回路や部屋に限定するのかも選択のポイントです。全負荷型は安心感がある反面、費用が高くなりやすい特徴があります。特定負荷型で必要な場所だけに給電する方が現実的なケースも多く、家庭の状況に応じた選択が重要です。
◇太陽光発電とセットで考える容量選び

太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせると、昼間に発電した余剰電力を夜間に利用できるため、自家消費率が高まり電気代の削減効果も期待できます。この場合、設置済みの太陽光パネルの発電量を基準に容量を決めるのが合理的です。
例えば、1日の平均発電量が10kWhで夜間の消費が7kWhなら、7〜10kWhクラスの蓄電池が適正といえます。発電量に対して容量が大きすぎると十分に充電できず、せっかくの設備を活かしきれません。逆に容量が小さすぎると夜間に不足が生じます。
また、太陽光をまだ設置していない家庭では、夜間の消費量を基準に考えるのがよいでしょう。特に固定価格買取制度(FIT)が終了した家庭では売電価格が低下するため、自家消費を重視した容量設定が経済的に有利になります。電気料金が高くなる夕方から夜間にかけて、どれだけの電力量をカバーしたいかを明確にすると、導入効果を最大化できます。
家庭用蓄電池は何年使える?寿命の目安と長持ちのコツ
家庭用蓄電池は高額な設備投資となるため、どれくらいの期間使えるのか気になる方も多いでしょう。寿命の目安を知り、適切な使い方を心がけることで、より長く安心して利用できます。
◇家庭用蓄電池の寿命はどのくらい?

家庭用蓄電池の寿命は、一般的に10〜15年程度 が目安とされています。これは、内部で使われる電池の種類や製造技術、利用環境によって変動します。特に家庭用で主流となっているリチウムイオン電池は、エネルギー密度が高く、小型でありながら大容量を実現できるため、住宅用途に最も広く普及しています。
メーカーが定める保証年数を寿命の目安としているケースも多く、10年保証や15年保証が付与されている製品もあります。実際の使用環境が良好であれば、保証期間を過ぎても動作を続ける場合もありますが、経年による劣化は避けられません。容量が目減りしていく点を考慮し、長期的に使う設備であることを念頭に置くことが重要です。
◇サイクル数と使用期間
蓄電池の寿命を表す際によく使われるのが「サイクル数」と「使用期間」です。サイクル数とは、蓄電池を満充電から空になるまで使用し、再び充電する一連の流れを1サイクルとして数えるものです。リチウムイオン電池では、通常 6,000〜12,000サイクル が目安とされ、1日1サイクルで計算すると10年以上使用できる計算になります。
一方で使用期間は、設置からどのくらいの年数を使えるかを指し、多くの家庭用蓄電池は 10〜15年 程度とされています。つまり「サイクル数=性能低下の目安」「使用期間=物理的な経年変化の目安」と捉えるとわかりやすいでしょう。どちらも製品ごとに異なるため、購入時は両方を確認することが大切です。
◇寿命を迎えた蓄電池はどうなる?

蓄電池が寿命を迎えると、突然使えなくなるわけではありません。多くの場合は 容量が低下 し、充電できる電力量が徐々に減っていきます。その結果、「以前は一晩もったのに、今は数時間で電力が切れる」といった不便が生じます。また、充放電効率の悪化によって電力の無駄が増えたり、動作時間が短縮することで停電時の安心感が薄れる場合もあります。
さらに寿命が近づくと、内部の電子部品の劣化や故障リスクが高まり、突然の不具合につながることもあります。寿命を迎えた蓄電池は、使えないわけではないものの性能低下による利便性の低下は避けられないため、適切な時期に交換やメンテナンスを検討することが必要です。
◇蓄電池を長持ちさせるコツ

家庭用蓄電池は使い方や設置環境によって寿命が大きく変わります。長持ちさせるためには、以下の点に注意すると効果的です。
・過充電や過放電を避ける
リチウムイオン電池は、フル充電や残量ゼロの状態を繰り返すと劣化が早まります。メーカーの制御システムである程度保護されていますが、可能な限り充電量を一定範囲で使うことが望ましいとされています。特に長期間放置する際は満充電や空の状態を避けるのがポイントです。
・設置環境を整える
蓄電池は高温・低温に弱く、直射日光や極端な温度差のある場所では劣化が進みやすくなります。屋外設置の場合は雨風や日差しを避けるためのカバーや屋根が推奨され、屋内設置でも換気や温度管理に注意が必要です。
・定期点検やメンテナンスを実施する
長期使用を前提とする設備のため、年に一度程度は点検を受け、異常がないか確認することが推奨されます。メーカーや施工業者のアフターサービスを活用することで、不具合の早期発見や寿命の延長につながります。
・適切な容量を選ぶ
過大な負荷をかけ続けると寿命を縮める原因となります。家庭の電力消費に対して適切な容量の蓄電池を導入することで、負担を分散させ長寿命化につながります。
【あわせて読みたい】
V2Hと蓄電池の違いを徹底比較

◇V2Hと蓄電池の基本的な違いとは?
V2H(Vehicle to Home)とは、EVやPHEVに搭載された大容量バッテリーに貯められた電気を家庭に供給する仕組みのことです。車を「走る蓄電池」として活用する発想で、停電時には家庭用の非常電源としても機能します。
大容量バッテリーを備えるEVは、車種によっては数十kWhの電気を備えており、家全体の電力を数日間まかなえる場合もあります。ただし、V2H単体には蓄電機能がなく、あくまで車のバッテリーを活用する仕組みである点に注意が必要です。また、すべてのEV・PHEVがV2Hに対応しているわけではなく、対応車種に限定される点も特徴です。
一方、家庭用蓄電池は住宅に固定して設置する設備で、外部からの電力を貯め、必要に応じて放電する機能を持ちます。設置後は常に家庭内で利用可能であり、太陽光発電との相性も良好です。車を外出で使っているときでも電気を貯めておけるため、安定して家庭を支える電源として機能するのが強みです。
◇利用できるタイミングの違い
V2Hと蓄電池の大きな違いは「利用できるタイミング」にあります。V2HはEV・PHEVが自宅に停まっているときにのみ使用できます。つまり、日中に車を通勤や買い物で使っている間は、家庭に電気を供給することはできません。したがって、車を日常的に長時間利用する家庭では、非常時や自家消費用途としての稼働時間が限られる可能性があります。
一方で蓄電池は常に住宅に設置されているため、外出に左右されません。太陽光発電で昼間に発電した電気を貯めて夜間に使うといったサイクルも安定して行えます。日常の電気代削減を重視する家庭や、夜間の電力利用が多いライフスタイルには蓄電池のほうが適しています。
◇蓄電できる容量の違い
容量面ではV2Hに軍配が上がります。一般的な家庭用定置型蓄電池は3〜15kWh程度が主流で、停電時には冷蔵庫や照明、通信機器など最低限の生活を支える規模が中心です。
対してEVのバッテリー容量ははるかに大きく、日産リーフで40〜60kWh、トヨタbZ4Xで71.4kWh、さらに高級EVのメルセデス・ベンツEQSでは100kWhを超えます。このため、V2Hを利用すれば長期停電にも十分対応できる大容量の電源を確保可能です。
ただし、常に大容量を有効活用できるとは限らず、外出時や車を使用中は家庭への給電ができない点が制約となります。一方で蓄電池は容量が小さい分、設置場所を選ばず、日常的に安定して使える点が魅力です。
◇導入コストと費用対効果の違い
導入費用はどちらも高額ですが、比較の仕方によってコストパフォーマンスが異なります。V2H機器は本体価格で55〜100万円程度、工事費込みで90〜130万円前後が一般的です。加えてEV・PHEV本体の購入費が必要ですが、バッテリー容量が大きいため「1kWhあたりのコスト」で見ると割安になるケースが多いです。例えば容量66kWhのEVで車両価格539万円の場合、単純計算で1kWhあたり約8万円。これにV2H設置費を含めても1kWhあたり約10万円となり、容量1kWhあたり平均18万円超の家庭用蓄電池より低コストで済む場合があります。
一方、家庭用蓄電池は本体+工事費で容量1kWhあたり18〜20万円程度が目安で、10kWhモデルなら200万円前後かかることもあります。導入費用は高いものの、太陽光発電との併用で日常的に確実に電気代を削減できる点や、外出中でも電力供給を維持できる点が強みです。
また、両設備とも国や自治体の補助金が活用可能で、V2Hは上限50万円程度の補助が出る地域もあります。蓄電池も1kWhあたり2万円などの補助制度があり、ZEH住宅や災害対策の観点で支援が充実しています。導入を検討する際には、補助金情報を必ずチェックすることが費用対効果を高める重要なポイントです。
蓄電池設置工事の流れと工事費用相場

引用元:フォトAC
蓄電池設置工事は現地調査から始まり、配線工事や動作テストを経て完了します。価格や工事費用は容量や品質によって異なるため、慎重な選択が求められます。
◇蓄電池設置工事の流れ
蓄電池の設置工事は、まず現地調査を行い、住宅の屋内外の配線状況や設置スペースを確認します。その後、蓄電池本体やパワーコンディショナを設置する場所を決定し、必要な配線工事と制御装置の設定を行います。工事が進む中で、動作テストと試運転が実施され、問題がなければ工事が完了します。
一般的には1~2日ほどで完了しますが、住宅の配線状況や既存の太陽光発電システムとの連携によって工程が変動することもあります。そのため、事前にしっかり確認することが重要です。信頼性のある調査によると、設置不備があると蓄電池のパフォーマンスが低下することがあるため、事前調査と適切な施工設計が解決の鍵となります。
◇太陽光発電蓄電池の価格
太陽光発電蓄電池の価格は、容量やメーカー、機能性によって大きく異なります。最新のモデルは高性能で長寿命の傾向があり、価格が高めに設定されることが一般的です。反対に、型落ちのモデルは比較的安価で購入可能ですが、充放電効率や保証内容において最新型に劣ることがあります。
市場調査によると、蓄電池の需要拡大と競争激化により、今後価格が下がる可能性も指摘されています。ですが、導入タイミングを見計らうことも重要です。ライフプランや電力使用量を考慮しながら、最適な機種を選択することが推奨されています。
◇蓄電池の工事費用相場
蓄電池の工事費用は平均で22.5万円という調査結果があります。この費用には配線工事や制御装置取り付けのコストも含まれています。ただし、施工の品質によって費用に差が出ることがあり、工事の質が低い場合、蓄電池の性能を十分に発揮できず、故障リスクが高まる可能性もあります。
そのため、初期費用がやや高くても信頼できる施工店に依頼する方が、長期的にはコストパフォーマンスが良いという分析がされています。複数の施工業者から見積もりを取得し、価格と品質のバランスを慎重に吟味することが重要です。
太陽光発電蓄電池の設置にかかる費用を抑える方法
補助金制度や0円ソーラー、型落ち蓄電池、相見積もりを活用することで、導入コストを抑える方法があります。慎重な選択と検証が重要です。
◇補助金制度を活用する

自治体や国が実施する補助金制度を利用すれば、蓄電池や太陽光発電システムの導入コストを大幅に軽減できる可能性があります。
これらの補助金は、特定の要件を満たす住宅用蓄電池や太陽光発電システムを対象に提供され、給付額は数万円から数十万円までさまざまです。複数の行政機関が異なる補助金を提供している場合もあるため、事前に情報収集を行い、申請手続きをしっかりと進めることが重要です。
◇0円ソーラーによる導入を採用する

初期費用を抑えるための手段として注目されているのが、0円ソーラーと呼ばれるリース契約です。
業者が機器を提供し、利用者は月々の利用料や売電収益の一部で支払いを行います。初期投資の負担が少なくなるメリットがありますが、長期的に見ると購入よりも総額が高くなる可能性があるため、シミュレーションを行って費用対効果を検証することが大切です。
◇型落ちした蓄電池を選ぶ
最新モデルは価格が高い傾向にありますが、型落ちモデルでも実用に十分耐える蓄電池を割安で購入できることがあります。
市場分析によると、型落ちモデルは性能面でやや劣るものの、必要な容量を確保できればコストパフォーマンスは高くなることが報告されています。購入時には、保証やアフターサポートの有無をよく確認し、長期的な安心を確保することが大切です。
◇相見積もりを取る
同じ機器を導入する場合でも、販売会社や施工店によって価格やサービス内容に差があります。
複数の業者から相見積もりを取得し、工事費や保証期間、施工品質などを総合的に比較検討することで、平均5~10%程度の費用削減が期待できるデータもあります。信頼できる業者を選びつつ、費用を抑えることが得策です。
【あわせて読みたい】
失敗しない蓄電池工事店の選び方

蓄電池の性能を最大限に活かすには、信頼できる工事店選びが欠かせません。施工技術や保証内容、対応の丁寧さなどを見極めることで、長期的に安心できる導入が可能になります。
◇工事見積で必ずチェックすべきポイント

家庭用蓄電池の設置では、本体価格だけでなく工事費用の内訳を正しく理解することが重要です。見積書を受け取ったら、まず「機器代」と「工事費」が明確に区分されているかを確認しましょう。工事費には基礎工事・機器設置工事・電気工事の3要素が含まれるのが一般的で、それぞれが省略されていないかが信頼性の判断材料となります。
基礎工事は蓄電池を安定して設置するために不可欠で、重量物を支えるために鉄筋入りコンクリートが使われるケースも少なくありません。これを簡易的に済ませようとする業者は注意が必要です。また、電気工事は第二種電気工事士以上の資格を持つ技術者が行わなければならず、資格者が施工に関わっているかも確認すべきポイントです。見積が極端に安価な場合は、人件費や安全措置を削っている可能性もあるため、費用の安さだけで判断するのは危険です。
◇メーカー指定工事店IDで安心を確保
安心して施工を任せるためには、工事店がメーカーの指定工事店IDを取得しているかを確認しましょう。これはメーカーが実施する研修を受け、一定の知識・技術水準を満たした工事店にのみ発行されるものです。指定工事店IDを持つ業者であれば、マニュアルに沿った正しい手順で工事が行われるため、施工品質のばらつきを抑えることができます。
反対に、認定を受けていない業者の中には、必要な部材を省いたり施工スピードを優先したりすることでコストを下げているケースも見られます。蓄電池は10年以上使う設備ですから、設置時の品質が寿命や安全性に直結します。工事見積の段階で「指定工事店IDの有無」を確認することが、安心できる業者選びの第一歩となります。
◇施工実績を見れば業者の力量がわかる
工事店の信頼性を測るもう一つの方法が施工実績の確認です。家庭用蓄電池の設置はまだ比較的新しい市場のため、経験が浅い業者も少なくありません。業者のホームページには施工実績や事例紹介が掲載されていることが多く、過去にどのような規模・環境で工事を行ったかを把握できます。
また、直接問い合わせて「これまでに何件施工したか」「自分の地域での施工実績はあるか」と聞くのも有効です。地域での実績があれば、設置環境の特徴や自治体補助金の申請経験も豊富である可能性が高まり、安心して任せやすくなります。口コミサイトの評価は参考になりますが、過剰な評価や意図的な書き込みもあるため、あくまで補助的な情報と捉えるのが賢明です。
◇保証とアフターフォロー体制は妥協しない
蓄電池は長期利用を前提とするため、施工後の保証やアフターフォローは妥協できない要素です。メーカー保証は本体やパワーコンディショナーに付帯しますが、加えて工事保証があるかどうかを必ず確認しましょう。基礎の固定や配線不良によるトラブルは、工事保証が適用されるか否かで修理費用の負担が大きく変わります。
さらに、日本は地震や台風などの自然災害が多いため、自然災害補償の有無も重要です。積雪や水害など地域特有のリスクに対応した補償があるかどうかは、業者によって異なります。加えて、定期点検サービスや異常時の駆けつけ対応が整っているかも長期利用の安心につながります。特に「連絡すればすぐに点検に来てくれるか」は、非常時に大きな差を生むポイントです。
安価な見積に惹かれて保証やフォロー体制を軽視すると、結果的に修理費やメンテナンス費用がかさみ、トータルコストが高くなることもあります。価格だけでなく、保証とアフターサービスを含めた総合力で業者を比較することが、失敗しない工事店選びの秘訣です。
埼玉県でおすすめの太陽光発電会社3選
株式会社カンエイ、恒電社、ウェーブは、いずれも高い技術力と信頼性を備え、蓄電池システムの施工からアフターサポートまで対応しています。
◇株式会社カンエイ
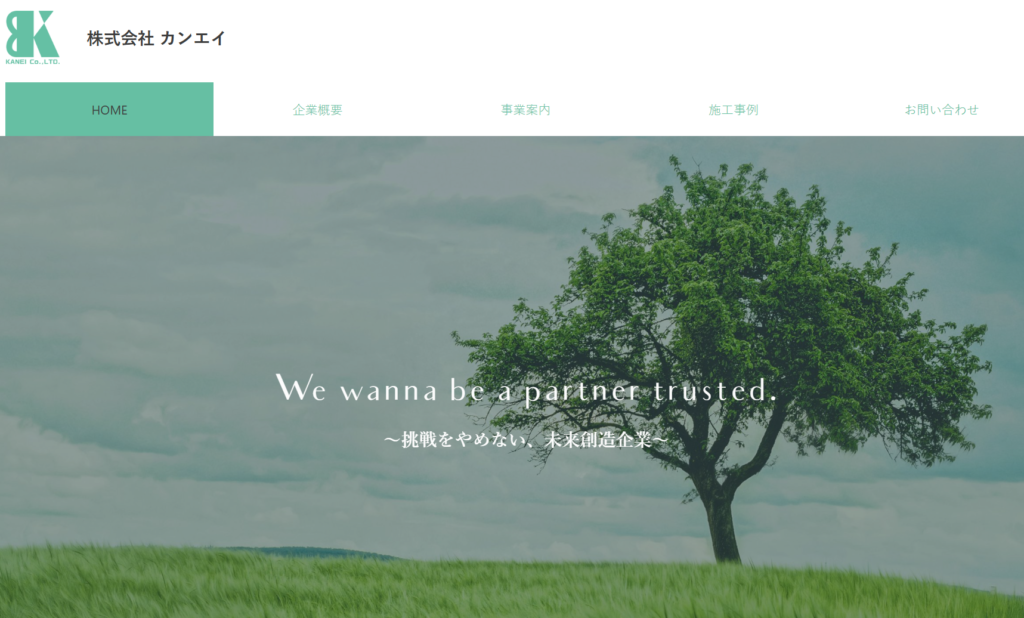
株式会社カンエイは、埼玉県さいたま市南区に本社を置き、2018年に設立された建築・電気・空調・土木など幅広い施工事業を手掛ける会社です。
資本金は2000万円で、建設業許可をはじめ、電気工事業や土木工事業、解体工事業など多様な許認可を取得し、高い技術力と信頼性を誇っています。
同社は主に太陽光発電システムの設計から機器調達、施工、申請業務、そしてアフターサービスまでを一貫して提供するワンストップサービスを展開しています。
環境に優しいエネルギーの推進とCO2削減に積極的に貢献しており、近年では太陽光発電所の盗難対策商品も取り扱っています。
さらに、施設の配置や用途に応じた最適な空調システムの選定と施工工事も行い、快適な室内環境づくりをサポートしています。
施工事例も多数公開されており、大規模な設備の更新や集中型から分散型へのパワーコンディショナー交換など、顧客のニーズに応じたきめ細やかな対応が特徴です。顧客満足を重視し、安全かつ高品質な施工を行うことで、信頼を築き上げています。
また、同社はさいたま市内に倉庫を保有し、物流面でも効率的な運営を行っています。会社としてはSDGs認証企業や多様な働き方実践企業としても認定されており、社会的責任を果たしつつ柔軟な働き方を導入しています。
地域社会への貢献と持続可能な経営を目指し、社員一人ひとりが誠実に取り組む企業文化が根づいています。
株式会社カンエイは、高度な技術力と幅広い事業領域を持ち合わせた企業として、今後も環境に配慮した快適な住環境とエネルギーシステムの提供に注力し続ける企業です。
| 会社名 | 株式会社カンエイ |
| 所在地 | 〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所7-6-8 3F |
| 電話番号 | 048-816-4304 |
| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |
| 公式ホームページ | https://kanei.co.jp/ |
信頼と実績を基盤に、お客様のニーズに応えた最適な提案とサービスを提供することを使命としています。
株式会社カンエイの口コミ評判記事はこちら!
▼カンエイは住宅用太陽光発電の販売から施工、点検、サポートまで一貫対応
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇株式会社日本エコシステム

株式会社日本エコシステムは、1997年に設立され、太陽光発電システムの販売・施工を中心に、省エネ製品全般の取り扱いを行うリーディングカンパニーです。住宅用の太陽光発電では約4万棟以上の販売施工実績を持ち、公共・産業用も含め全国で多数の導入実績があります。
独自の安全管理と技術力により、地域の環境や設置状況に合わせた最適なエネルギーシステムを提案し、信頼を集めています。主要事業は太陽光発電システム、蓄電池、V2H、オール電化の販売および施工で、関連する付帯業務も包括的に対応しています。
「エコらしく、ヒトをつくり、モノをつくり、未来をつくる」という理念のもと、再生可能エネルギーの普及に努め、持続可能な社会づくりを支援。これまでの販売実績は640MW超に達し、年間のCO2削減量は杉の木約1,876万本が吸収する量に相当します。
さらに、お客様に安心して長く利用いただくためのアフターサービスや自然災害補償も提供しています。日本コムシス株式会社のグループ企業として、豊富な資金力と信頼の基盤を持ち、全国対応の体制で環境負荷の低減と快適な暮らしの実現に尽力しています。
| 会社名 | 株式会社日本エコシステム |
| 所在地 | 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作2-4-15 |
| 電話番号 | 048-681-5610 |
| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |
| 公式ホームページ | https://www.j-ecosystem.co.jp/ |
以上のように、株式会社日本エコシステムは多彩な事業と確かな技術力で、再生可能エネルギー分野におけるトップ企業として社会に貢献し続けています。
▼日本エコシステムの太陽光発電が共働き家庭や子育て世代に与えるメリット
◇サンテックパワージャパン株式会社

サンテックパワージャパン株式会社は、1967年に設立され、東京都新宿区に本社を置く太陽光発電システムの専門企業です。
40年以上にわたる太陽電池モジュールの販売実績と25年以上のシステム設計経験を持ち、住宅用から商業用、産業用まで幅広い分野で高性能な太陽光発電ソリューションを提供しています。
同社は、太陽光発電システムの開発・販売に加え、技術サポートや太陽光発電所の開発・保守管理、遠隔監視システムの販売・設置、O&M(運用・保守)サービスを行っています。特に、高い技術力を誇る長野テクニカルサポートセンターを有しており、製品の品質管理や技術サポートで顧客の信頼を得ています。
また、太陽光発電だけでなく、パワーコンディショナーや蓄電システムなどの周辺機器も手掛け、トータルなエネルギーソリューションを提案。環境負荷の低減や持続可能な開発目標(SDGs)への貢献を目指し、クリーンエネルギーの普及に積極的に取り組んでいます。
| 会社名 | サンテックパワージャパン株式会社 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-6-11 西新宿KSビル6F |
| 電話番号 | 0120-303-616 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式ホームページ | https://www.suntech-power.co.jp/ |
信頼性の高い製品と充実したサポート体制により、顧客満足度の高いサービスを提供している企業です。
▼サンテックパワーの産業用太陽光発電を紹介!信頼性と実績が強み
まとめ

太陽光発電蓄電池は、効率的な運用と長期的なコスト削減が期待される装置として注目されています。特に災害時の非常用電源として利用でき、電力の自家消費を促進するため、省エネにも貢献しています。これにより、蓄電池の需要は拡大しています。
蓄電池は外部電源から電力を化学反応で貯蔵し、必要なときに放電して使用します。太陽光発電と連携させることで、昼間に発電した電力を蓄電し、夜間や日照不足時に使用することが可能です。リチウムイオン型蓄電池が主流で、軽量でエネルギー密度が高いという特徴があります。また、技術進歩により充放電サイクル寿命が延び、長期的なコスト削減が期待されています。
蓄電池が注目される理由のひとつは、災害時に最低限の電力供給が可能な点です。また、電力会社からの電力買い取り価格が低下する中、太陽光発電で得た電力を自家消費する方が、光熱費削減に有効であるとされています。このため、省エネや災害対策を兼ねた蓄電池の導入が有効な選択肢となっています。
蓄電池設置工事は、現地調査から始まり、配線工事や動作テストを経て完了します。設置期間は1~2日程度が一般的ですが、住宅の配線状況や太陽光発電システムとの連携によっては、工程が変動することもあります。工事費用は、容量や品質によって異なり、平均22.5万円程度とされています。施工の品質により、費用に差が出るため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
蓄電池導入コストを抑える方法としては、補助金制度の活用、0円ソーラーリース契約、型落ち蓄電池の選択、相見積もりの取得があります。これらの方法を検討することで、費用を抑えつつ導入することが可能です。
埼玉県でおすすめの太陽光発電会社として、株式会社カンエイ、恒電社、ウェーブが挙げられます。いずれの会社も高い技術力と信頼性を持ち、施工からアフターサポートまで対応しています。
【あわせて読みたい】
▼【2025年最新版】蓄電池は後悔しやすい?理由と対策を紹介
